友松医院跡−遊郭時代を偲ばせる遺構

遊郭はいちおう公娼なので、そこで働く遊女たちは週1回以上の性病検査が義務づけられていました。検査で引っかかった遊女たちは「営業停止」を食らい、強制入院となります。
「性病絶対見つけてやるマン」の医師と、あの手この手でごまかそうとする遊女の化かし合いが、遊郭裏話として断片的に残っていることもあります。
場所によっては公営の病院が遊郭内に設けられていたのですが、高雄にも上の地図に「婦人病院」の名が見えます。
こういう病院は、遊郭という特殊な場所の性質上、遊女しか診ないのが特徴で性病または婦人科専門なことがほとんどでした。
その中の代表、大阪の「難波病院」がありましたが、詳しくはこちらをどうぞ。昔の日本、こんな「専門病院」があったのか(特に大阪府民)…と驚くに違いありません。
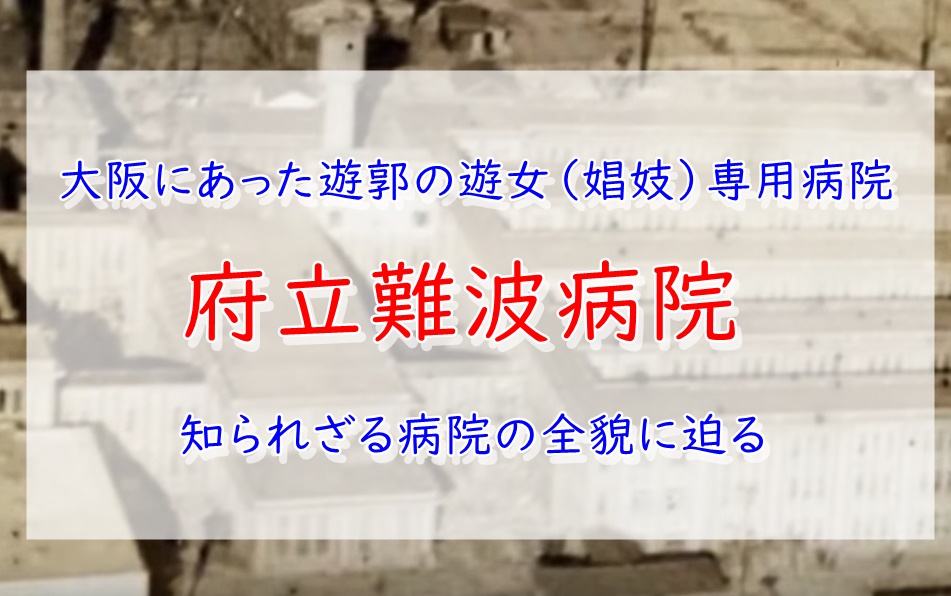
しかし、中には私営の病院も存在していました。
高雄市で知る人ぞ知る、ある建物があります。

高雄の塩埕の片隅に眠るこのレトロな建物。昭和初期に大流行したアールデコ、流線型をふんだんに使った「昭和モダーン建築」の典型であるこの建物、明らかに日本統治時代の建物だということがわかります。
こちらは駱栄金という医師が1930年に高雄に建てた、「友松医院」という名の病院でした。

彼は日本統治前の1890年(明治23)に新竹に生まれ、30歳にして台湾の医学学校を卒業。高雄で医院を開業したのは40歳とどちらかと言えば遅咲きの人でしたが、上の人士録では「新進有為ノ紳士ナリ」と紹介されています。
また、医師以外にも数々の会社の社外取締役を兼任しており、鹽埕地区の有望な人材、「鹽埕の五虎」の一人としてこれからの人材でした。
「友松医院」の肩書きは「外科」だったそうですが、実際は泌尿器科、性病を専門に扱っていました…これでもうピンとくるでしょう。

医院の位置は、遊郭から直線距離にして約500メートル、道も一本です。
「友松医院」は個人医院でしたが、駱栄金の本人は総督府認定の公医だった経験もあるので、総督府など公の機関とも関係はあったはず。だから、遊郭内の「婦人病院」では処理できない遊女や男性などの治療も行っていたことは、想像に難くありません。

経歴によると、駱栄金が開業したのは1930年なものの、最初は別のところで開業したらしく、現在の建物があるところへ引っ越し、この建物が完成したのは1936年とのこと。
1階が病院、2階が家族の居住スペースという、現在の個人病院によくあるスタイルとなっていたそうです。

高雄市の史跡に指定された友松医院、現在公費にて修復中とのこと。工事完了は2026年3月とのことで、何かしらの形で開放されたら筆者もはせ参じたいと思います。
また、友松医院や駱栄金の件も、深掘りするともっと色んなころが発掘されそうなので、開放され見学できたらさらに深掘りしていきたいと思います。

遊郭とは関係ないですが、友松医院の近くには総督府の医官(公務員としての医者)だった帖佐直喜が1933年(昭和8)に建てた帖佐医院跡が残っています。
こちらは友松医院より先に高雄市史跡となり、

こっちが史跡扱いされ友松医院がされないっておかしくね?
という声があがっていたそうです。
高雄遊郭のお話、今回はこれにて読み終わり。







