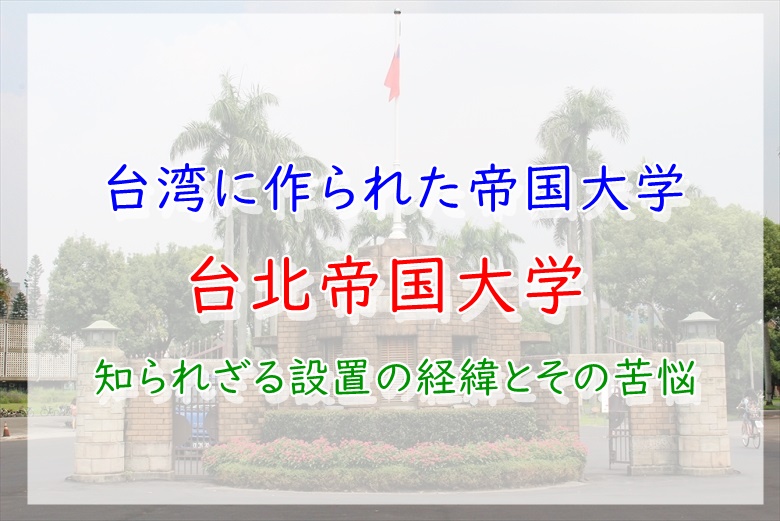國立台灣大学(NTU)。
11の学部に50以上の学科を備え、3万人ほどの学生が在籍している、台湾一の総合大学である。「台湾の東大」にふさわしい規模と実力を備えている。
前身は日本統治時代に創設された台北帝国大学なのは説明するまでもないが、その経緯についてはあまり知られていない。
今回は、その歴史を追っていこう。
台北帝国大学の種をまいた男と、花を咲かせた男
旧制台北高等学校をはじめ、台湾の教育制度に間接的ながら穴を開けたのは、時の首相原敬であった。原は1921年(大正10)に暗殺されるが、間接的に台湾教育史に関わっており、彼が蒔いた教育の種は引き続き台湾で芽吹くこととなる。
1924年(大正13)、10代目の台湾総督としてある男が台湾の地を踏んだ。

伊沢多喜男(1869-1924)という内務官僚である。
「日本初の普通選挙を行った内閣」として日本史で学ぶ加藤高明内閣で、伊沢は大臣の任命を受けとったのだが、彼はそれを断る。
その代わりにと、彼は言った。

台湾総督にさせてくれ
台湾総督というと、「総督」という名前の響きもあって地位が高そうな印象があるが、実は名前ほどでもない。時代は既に文官総督時代になっており、法律によって総督の権限は縮小されていた。よって、台湾総督は内務省官僚の1ポストに過ぎず、序列は東京市長より格下。
当然日本の内閣で大臣をやっている方が地位が高く、老後の恩給(年金)の額も全然違う。大臣を蹴っての台湾総督は、自ら二階級降格処分を申し出るに等しかった。
それなのに、彼はなぜ台湾総督を望んだのか。それを語るには、今でも台湾で語り継がれている、ある物語が絡んでくる。
1895年(明治28)、台湾は清から割譲され日本の統治下に入った。日本の統治が英国などの列強とひと味違っていたのは、いの一番に学校を作ったこと。

日本は植民地に対して格好をつけたかった
と李登輝氏が語る通り、これが台湾人インテリの平均的な日本統治時代の歴史観だが、「生かさず殺さず」の欧米型植民地支配とは明らかに何が違っていたことは確かである。
台湾にとって非常にラッキーだったのは、日本が世界でもまれに見る初等教育の鬼軍曹だったこと。
台湾に教育を広めるべく、日本はある男を台湾に派遣した。

彼の名は伊沢修二(1851-1917)。名字でわかる通り、台湾総督伊沢多喜男の兄である。ただし、兄といっても親子くらい年齢が離れている。
彼は弟と違い文部官僚として教育畑一筋を歩んだ人物で、特に音楽教育に力を入れた人であった。一度は誰でも歌ったことがある、「ちょうちょ、ちょうちょ、この葉に止まれ」の『蝶々』は、伊澤がスペインかスコットランドの古歌からメロディーを拝借したもの。
ある日、伊澤はある男が作ったオルガンの調律をお願いされた。浜松からわざわざ東京までオルガンを持って来た心意気に伊澤は承諾するものの、男は音楽のド素人。楽器を作るならちゃんと音楽理論を学ぶべきだと諭した。
男はそれに奮起して音楽理論を学び楽器メーカーの王者となるのだが、名前は山葉寅楠。

みんなお馴染みヤマハの創業者や
そんな彼が、
「台湾なんかもらってどうするんだ、フランスに売り払ってしまえ」
「台北なんて都市計画の失敗作。更地にして街を作り直してしまえ」
と、お雇い外国人にすらコテンパンの酷評だった台湾に赴任した理由は、やはり教育の普及だった。教育面において、日本はいきなり植民地にエースピッチャーを投入したのである。
日本の統治下に置かれた1895年、台北北部の芝山巌(しざんがん)に「芝山巌学堂」という小学校を設立した。四書五経を教える私塾程度の学校は点在していたものの、近代教育の学校は芝山巌学堂が初となり、今でも「台湾教育の聖地」となっている。
順調に思えた芝山巌学堂だが、1896年(明治29)に抗日ゲリラによって襲撃された。伊沢は日本に帰っており難を逃れたが、残っていた6人の教師(「六士先生」)は惨殺されてしまった。これを「芝山巌事件」と言い、台湾史に必ず出てくる出来事である。
実は、抗日ゲリラが襲撃することは事前に漏れており、周囲は避難するよう勧めた。が、教師側は

実に死に甲斐あり!
とその場を離れず、堂々と殺されたと言う。
彼らの死に様と犠牲精神は、今でも「芝山巌精神」という名前で台湾で知られている。伊沢修二も、教育に貢献した人としてそこそこ知名度がある日本人の一人である。
この事件のせいではないものの、伊沢兄は翌年、失意のうちに台湾を離れた。
その27年後、弟が総督として赴任した。
大学設立自体は、伊沢総督の前から決まっていたものの、彼は総督府として正式に「大学設置費」の予算を組み、在職期間のほとんどを帝国大学設立のために費やした。彼の総督としての志は、ぼんやりとした気体だった台北帝国大学計画を凝縮し、個体にすること。彼も兄が遺した意思を背負って挑んでいたのだろう。
文学的な表現をするならば、兄が蒔いた種が花開こうとした時、弟がそれを飾る花壇を作りに来たと言っていいかもしれない。